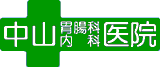 |
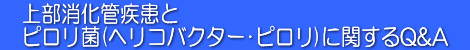 |
| A.ピロリ菌って何? | |
 大まかに言えば、大きさ1000分の3~4mm、大腸菌や納豆菌と同じく細菌の一種です。しかし菌体の端に長い鞭毛を持ち、尿素からアンモニアを産生する能力を持つといった特徴を有する独特の細菌です。 大まかに言えば、大きさ1000分の3~4mm、大腸菌や納豆菌と同じく細菌の一種です。しかし菌体の端に長い鞭毛を持ち、尿素からアンモニアを産生する能力を持つといった特徴を有する独特の細菌です。「通常の胃には細菌はいない」 長い間、誰からもそう信じられてきました。胃の中には強い胃酸が存在するからです。ところが1982年オーストラリアの病理学者が胃の中に生息する細菌を発見!しかもその細菌、つまりピロリ菌は、世界中多くの人の胃に既に棲みついていることがわかったのです。 |
|
| B.ピロリ菌を持っている人はどの位いるのか? | |
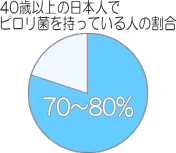 人種により、また年令により様々ですが、40歳代以上の日本人では人口の70~80%が感染しています。これより若い年令層ではもっと少なく、衛生環境が良くなると感染率が減ると考えられています。 人種により、また年令により様々ですが、40歳代以上の日本人では人口の70~80%が感染しています。これより若い年令層ではもっと少なく、衛生環境が良くなると感染率が減ると考えられています。ただし口から胃に入って感染(経口感染)すること以外、その経路はまだ明らかになっていないようです。 |
|
| C.ピロリ菌はどんな悪さをするのか? | |
| 感染してすぐに急性胃炎を引き起こすといわれていますが、症状の程度は人により様々のようです。 胃に住み着いたピロリ菌は、産生するアンモニアやタンパク質により胃の粘膜を傷害し、長期的には慢性胃炎を引き起こすことがわかっています。 他に判っていることを列挙すると、 ① 胃潰瘍の人の70~80%、十二指腸潰瘍の人の90%以上にピロリ菌がいる。 しかしピロリ菌を持っていても大半の人は潰瘍にならず、潰瘍になる人は一握り。 ② 胃癌になった人の多くでピロリ菌感染が確認されている。 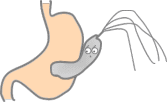 ただしピロリ菌に感染している人でも胃癌を発病するのはごく少数。 ③ 胃のリンパ腫の一種(MALTリンパ腫)の原因にもなっているとみられる。 ただしこれは胃癌よりもっと少ない。 ④ 非潰瘍性消化不良症(Non-Ulcer Dyspepsia [NUD]) とも 「いわゆる胃炎」症状ともいわれる「胃もたれ・吐き気・胃部不快感」と いった症状の一部を、ピロリ菌が引き起こしているらしい。 |
|
| D.ピロリ菌を退治(除菌)すると何が良いか? | |
| 一度なった胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発が非常に少なくなる。再発防止の為に服薬継続を余儀なくされていたことから、(理論上は)解放される。はっきり判っているのはこれに尽きます。平成12年11月からは医療保険でも潰瘍に対する除菌治療が認められるようになりました。 「除菌すると胃癌になりにくくなる」ことを示唆する研究がいくつか見られますが、まだ検討段階です。 当院も参画している山形県臨床ヘリコバクター・ピロリ研究会の調査(自主研究)でも、除菌と胃癌との関係に力点がおかれ現在研究が進められています。 |
|
| E.ピロリ菌の除菌治療とはどのようにするのか? | |
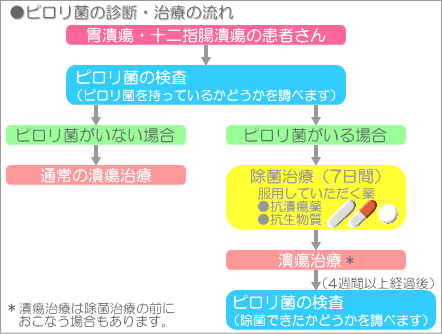 保険治療では 胃潰瘍または十二指腸潰瘍と 診断のついた方に対してのみ、 ピロリ菌の検査・除菌治療が認められています。 潰瘍かどうかは通常、内視鏡検査 (または胃レントゲン検査)によって診断します。 次にピロリ菌が胃の中に存在するかどうかを検査します。主な検査方法としては、 ◆内視鏡を使う方法◆ (内視鏡検査で潰瘍の診断がついたらそのままゴマ粒大の胃の組織を採取して検査します。) A.迅速ウレアーゼ試験 ピロリ菌に特有のウレアーゼ活性により尿素がアンモニアに変化するかどうかを見る検査法です。約30分で判定できる点がすぐれています。 B.鏡検法 胃の生検組織そのものにピロリ菌が付着していないかを調べます。陽性と出た場合には確実性の高い点が特徴です。 ◆内視鏡を使わない方法◆ 尿素呼気試験法 検査薬として飲んだ尿素がピロリ菌に特有のウレアーゼ活性によりアンモニアに変化するかどうか、呼気を集めて測定する検査法です。陰性をもっとも正確に判断できる検査法と考えられています。 があります。 当院では、ピロリ菌の存在を判定するのには迅速ウレアーゼ試験または鏡検法を主に用いています。 検査で、ピロリ菌がいることを確認したら治療を行います。抗潰瘍薬の1種類と2種類の抗生物質を7日間服用していただきます。潰瘍治療と同時に除菌治療をする場合と、まず潰瘍を治してから除菌する場合があります。 すべての治療が終了した後、4週間以上経過してから、ピロリ菌が除菌できたかどうか、もう一度検査を行います。このときは尿素呼気試験法で判定する場合が多いです。 |
|
| F.ピロリ菌の除菌の成功率はどれくらい? | |
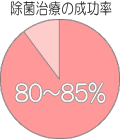 治療成績と耐性菌(薬が効かない細菌)出現の危険性を検討した結果、現在の組み合わせが選ばれました。 治療成績と耐性菌(薬が効かない細菌)出現の危険性を検討した結果、現在の組み合わせが選ばれました。このやり方では80~85%程度の除菌成功率が見込まれています。 |
|
| G.除菌治療は安全か、副作用はないのか? | |
| 除菌治療で飲んでいただく薬はいずれも従来から広く使用されている薬剤で、安全性は充分に確認されているものばかりです。その意味では除菌治療は非常に安全性の高い治療といえます。もちろんそれぞれの薬には、発生する可能性のある特有の副作用はありますが、そのほとんどは軽微なもので(味覚異常・軽い下痢や軟便など)、服薬を中断せざるを得ない重大な副作用は稀と考えられています。 服薬時の副作用とは別に、除菌治療によって後から食道・胃・十二指腸に起こる変化がいくつか指摘されています。除菌治療により胃酸の分泌が回復することが主な原因と考えられていますが、自覚症状を伴うものとしては食道への胃酸の逆流による胸焼け症状が最もよく知られています。もちろん万一そのような症状が出てしまった場合でも、服薬などによる治療が可能です。 もっと詳しくお知りになりたい方は、山形県臨床ヘリコバクター・ピロリ研究会の調査登録の説明文に、起こりうる危険・問題点について(可能性の極めて少ないものまで含めて)列記されていますので、ご参照ください。 |
|
| H.一度除菌治療に成功したら二度と内視鏡検査はいらないのか? | |
| 残念ながらそうではありません。内視鏡を使わずにピロリ菌の有無だけを見る方法は既に実用化していますが、本当に潰瘍が再発していないのかどうかなど、潰瘍の状態を診るためにも、また良性の潰瘍と外見上紛らわしい胃癌の見落としを防ぐためにも、除菌後も半年から一年毎に一度内視鏡観察が望ましいと考えます。これは潰瘍のない方に対しても、年1回の胃癌検診をお勧めすることと考え方は変わりません。除菌治療がまだ完全に評価の定まった治療でないだけに、内視鏡による定期的な経過観察は必要と考えています。 |
|
| I.除菌治療を受けたいがどうすればよいか? | |
| まず当院にお電話ください(℡ 0238-21-3208)。日時を約束して来院していただくのが最良の方法と考えます。 |
|
| 付録.山形県臨床ヘリコバクター・ピロリ研究会の調査とは? | |
| 山形県臨床ヘリコバクター・ピロリ研究会は、山形県立中央病院が中心となって平成12年10月に発足した会で、当院はもちろん山形県内の多数の病院・診療所が参画・賛同している会です。この会では適正なピロリ菌除菌治療を推進すると同時に、会に賛同していただいたピロリ菌感染患者さんを登録し追跡調査を行なうことにより、除菌治療の成績や胃癌との関連性などを調べ、ひいては潰瘍や胃癌治療の為に役立てる事を目的にしています。 当院でも調査登録にご協力をお願いしておりますが、もちろん強制ではありません。登録の際にお渡しする会の説明文の全文は右のようなものです。 調査登録の説明文を見る |
|