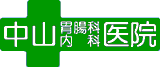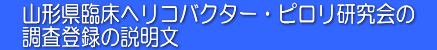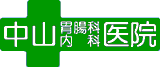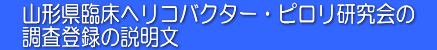患者さんへ:ピロリ菌と除菌療法について
|
| 1)ヘリコバクター・ピロリ除菌療法とはどんなもの? |
|
あなたの病気は「消化性潰瘍(胃潰瘍または十二指腸潰瘍)」と思われます。
最近、この病気が再発したり、治りにくくなったりする原因の一つに、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)という胃の中に存在する細菌が関係することが明らかとなってきました。またこの菌は慢性胃炎を引き起こし、慢性胃炎が高度に進行した患者さんの中から胃癌になる人が出てくる事が知られています。
世界の半数以上の人に感染している菌です。ピロリ菌に感染するとほぼ全例で胃炎が起こり多くの場合感染と胃炎が持続します。一部の人は胃潰瘍、十二指腸潰瘍を発症し再発を繰り返します。また、感染者のうち0.3~0.4%に胃癌が発症し、ピロリ菌に感染してない人の3~6倍胃癌が多いというデータが示されております。
多くの潰瘍は「胃酸の分泌を抑える薬」を服用することにより、治癒するようになりましたが、服用を中止すると再発することの多いやっかいな病気です。
「胃酸の分泌を抑える薬」と二種類の「抗薗薬」を朝、夕食後1週間服用(除菌療法)することにより除菌に成功すると、薬を縦続せずに潰瘍の再発を抑えられることが報告されており、世界的に潰瘍の治療法として定着しております。除菌療法は、従来の潰瘍を治す治療に加え、ピロリ菌を身体から排除することを目的としています。
潰瘍の患者さんは、除菌治療に引き続き「胃酸の分泌を抑える薬」を5~7週間服用します。期待される除菌率は80~90%ですので、10人に一人は除菌できない事になります。又、除菌されても一部の人は潰瘍が治癒しなかったり再発する事もあります。
◎ 除菌療法による効果
組織学的胃炎の治癒、胃・十二指腸潰瘍の治癒、再発抑制効果です。その他の効果について例えば、胃癌の抑制効果などについては、現在の所不明です。
◎ 除菌後におこりうる問題
除菌して胃が健康な状態に戻ることによって、十二指腸びらんや胸焼けなど酸逆流症状を発症する事があります。胃酸逆流によって食道や胃噴門部の腺癌が増える恐れも一部では指摘されていますが、科学的に証明されていません。また、除菌が不成功に終わった場合、ピロリ菌が耐性化する恐れがあります。その他、除菌したために体調が良くなって体重が増える場合もあります 。
内視鏡検査などで潰瘍がわかり、ピロリ菌が証明された場合、除菌療法を受けるかどうかはあなたが決定して下さい。除菌療法を受けなくても従来の治療を適切に行ない同等に治癒する事が出来ます。
|
| 2)予想される危険性などについて。 |
|
「胃酸の分泌を抑える薬」は胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療薬として、「抗菌薬」は種々の細菌感染症の治療薬としてすでに広く使われており、安全な薬として確立しています。
しかし、除菌療法では、「胃酸の分泌を抑える薬」あるいは「抗菌薬」は、通常使用される量より多い量の投与が必要です。その安全性については慎重に監視いたします。
主な副作用は、下痢・軟便、味覚異常、食欲不振等の消化器症状、発疹等の皮膚症状、などが報告されています。その他の副作用もあわせた全体の発現頻度20~40%です。 また、2~5%に治療中止となるような程度の強い副作用(下痢、発熱、発疹、喉頭浮腫、出血性腸炎)が報告されております。
◎ 副作用の症状に応じて次のようにして下さい。
軽い下痢・軟便、味覚異常の場合
自分の判断で薬ののむ量や回数を減らしたりせずに1週間のみ続けて下さい。
ただし、下痢、味覚異常がひどくなった場合は主治医または薬剤師に相談して下さい。
発熱、腹痛を伴う下痢、あるいは下痢に血や粘液が混じっている場合
直ちに薬をのむ事を中止し主治医または薬剤師に連絡して下さい。
|
| 3)他の治療法の有無および内容について。 |
|
潰瘍を治すには従来の酸分泌抑制剤による治療方法と、この除菌療法とがあります。除菌療法を受けるかどうかは、あなたの自由です。あなた自身が決めて下さい。除菌療法については、日本では、「ヘリコバクター・ピロリを取り除くこと」を承認されている薬は、この「胃酸の分泌を抑える薬」と「抗菌薬」を服用する(除菌療法)以外はありません。例えばピロリ菌に効果のあるといわれている食品やその他の薬品ではピロリ菌を完全に除菌する事はできません。
|
| 4)除菌後の検査に関して。 |
|
除菌、潰瘍治療後4週以降に胃内視鏡検査を行います。その際ピロリ菌の有無について検査を行い、陰性の場合さらに他の検査で確認します。
潰瘍の再発、酸逆流症や胃癌の有療をみるために、1~2年に1回の胃内視鏡検査などによる経過観察を受けられることをお勧めします。
|
| |
|
山形県臨床ヘリコバクター・ピロリ研究会の
調査(自主研究)に参加して頂くに際して
|
| 1)調査の目的 |
|
消化性潰瘍の治療法の一つとしてピロリ菌の除菌療法が厚生省により認可されました。ピロリ菌の除菌によって潰瘍の再発が抑制される事は既に明らかにされています。
この調査はピロリ菌除菌に関する以下の点を明らかにしていき、今後の診療に役立てる事を目的としています。
①山形県における除菌率、副作用、再発率、耐性菌の割合、新たにおこる問題点
②ピロリ菌除菌による胃癌発生の抑制効果の有無
③除菌治療の有舞による酸逆流症と、食道、噴門部腺癌の発生頻度の違い
|
| 2)方法、プライバシーの保護に関して |
・
・
・
・ |
感染診断、除菌治療又は潰瘍治療は、保険診療によって適切に行われています。
この調査、登録に同意された方については、アンケート内容及び検査、治療、経過観察で得られた結果を記録し、下記の事務局へ郵送し、専用コンピューターに登録します。
ピロリ菌の一部は培養し、菌の特徴などを分析する事があります。ピロリ菌の分析のため、血液等と異なりあなたのプライバシーに関わる事はありません。
この記録は、集計し医学雑誌などに発表される事があります。また発癌率の抑制効果をみるために地域がん登録などの疫学調査を参考にすることがあります。この場合もあなたの名前など個人的な情報は一切わからないようにしますので、プライバシーは完全に守られます。
|
|
|
| 3)自由意志による参加、同意、撤回の自由 |
|
この調査に参加するかどうかはあなたの自由です。不明な点は担当医師に質問して頂き、十分に時間をかけて決めて下さい。調査、登録は、研究の主旨をご理解頂き、同意された方のみ行います。あなたがアンケートの記入、登録に同意されない場合でも、今後の診療で不利益を受ける事は全くありません。
また、参加へ同意した後でも、あなたの気持ちが変わったときは、いつでもその同意を撤回できます。それにより何ら不利益を受ける事はありません。
山形県臨床Helicobacter
pylori研究会
事務局:山形県立中央病院 内科消化器グループ |
|
|
|
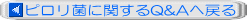 |